

「魅力」コーナー第3回からマイナーチェンジです!今回からテーマ発案者を先頭に後続レビュアーが,つっこみを入れつつ進行するリレーエッセイになります.リニューアル一発目は不肖えむはし軍曹がつとめさせていただきます.
今回のお題は「X-MEN いきなり最終回!」です.とにかく長い連載で基本的に最終回がないのがアメコミの常.あえて最終回を考えてみましょうというのがテーマです.そういえば「ドラえもん」最終回なんてのも昔あったなぁ...さて,どんな名最終回,珍最終回が生まれるやら..乞うご期待!
(文責 えむはし軍曹 2002/03/22)
■ レギュラー執筆
ニューヨーク,セイラムセンター,恵まれし子らの学園.外は延々と続く雨.チャールズ・エグゼビアはその寝室で人生の最期を迎えようとしていた...もうこのベッドで何日寝ただろうか?あのあわただしい毎日が嘘のように静かな日々が続いている.昨夜からラジオはつけたままだ.シャイアの先端テクノロジーに囲まれたこの学園には不似合いにクラシックなその機械からはオールディーズが雑音にまじって聴こえてくる.
「教授,起きてらっしゃったんですか.」
寝室に入ってきたのはケイト・プライド.元X-MENだ.最年少X-MENとして活躍した頃からすでに四半世紀の年月がながれ,その柔和な顔には皺が刻まれている.
「おはようございますチャーリー.よく眠れました?」
エグゼビアは微笑むだけだ.もう話すこともままならないほど衰弱しているのだが,かつての教え子に弱い自分は見せたくないのだ.彼ならばテレパシーで会話する事は造作ないのだが,あえて最近は使わないようにしている.意固地かもしれないと自分でも思うが,病床に伏しても威厳ある父の姿を見せたかったのだ.弱音は吐くまい,まだ自分は大丈夫だ.その気力だけで病を克服してきた.思えばこの老紳士の生涯はそうした頑健な気構えに支えられてきたのだった.今の今まで休んだことなどなかった.
「カートがね,ブルーベリーを贈ってきてくれたんですよ.今年も教会の庭で沢山とれたんですって.もういい年なのに電話口ではしゃいじゃって,ほんと子供っぽいんだから.」
沢山の子供達にであった.指導と呼べるようなものではなかったが,いつも彼らとともに居た.何かを教えたのかと問われれば大した事を教えた訳ではないのかもしれない.しかし,確実に彼らは何かを学び巣立っていった.今は彼らが新しい世代にその何かを伝えようとしている.「夢」といえば聞こえがいいのかもしれないが,実のところは頑固さだけだった.誰にも差別されたくない,差別をしたくない,その思いを強くもちつづけただけだった.しかし,それでも子は育っていく.いつしか男はそんな頑固さを自身の言い訳にして,自らをふりかえることを辞めたのだった.私の全てはX-MENだ..そう思い込んでから何十年経ったのだろう?
「..それでね,オロロがブルーベリーパイ作るってはりきっちゃって,ふふふ.午後にはローガンもスコットも来るのよ.ひさしぶりにちょっとしたパーティーになりそうね.」
懐かしい名前に頬が緩む.自分に勝るとも劣らない頑固な教え子たちが顔をだすのか.まさに生き写しの頑固者だ!目を閉じれば彼らの言動が手にとるように思い浮かぶ.可愛げのない教え子ほど自分によく似たものだ.思わず苦笑してしまう.
ラジオはOtis Reddingの"FA FA FA"を流しはじめる.少し眠くなってきたようだ.
「ケイト,少し休もう.」
口で話したつもりだったが,それはテレパシーを介して発せられた.
長く続いた雨はあがり青空が顔をのぞかせる.ドアベルが鳴りケイトは出迎えに走っていく.寝室にはOtisの"FA FA FA"がいつまでも流れている...
ちょっとおセンチに書いてみました.やっぱりX-MEN=エグゼビアだと思うので,彼の死=X-MENの最終回という気がします.この時点でミュータントと人類の共存はできたのかできていないのかは不明にしておきました.目的が達成されるより夢が引き継がれていく方が希望があると思うんですね.で,最期はキティに看取ってもらいたいという個人的欲求が反映されています(笑).ちなみにキティちゃんは死んだピートとピーターに操を立てて生涯独身という設定です.マグニートーを絡めることができなかったのが失敗といえば失敗.うーん..どうしてもやおいっぽくなっちゃうから難しいね.マギーは..
(文責 えむはし軍曹 2002/03/22)
「チャールズ。お前はここで何をするつもりだ?」
磁界王の問いに車椅子の老人は無言だった。
ニューヨーク州セイラム・センター郊外。エグゼビア邸。今はこの邸宅を警察、FBI、果ては軍隊までが取り囲んでいた。
そのわずかに2年前。メンフィスに現れたアポカリプスとX-MENたちの激闘は悲劇へと変わってしまった。チームリーダーのストームは、魔神アポカリプスを打ち倒すべく、その力の最大限を放出した結果、かつて観測されたことのないほどの巨大なハリケーンを生み出してしまった。この威力はやがて、連鎖的に全地球的異常気象をもたらした。特にアメリカ本国では深刻な食料危機をもらたしてしまった。
そして、3ヶ月前のこと。たった一人のミュータントの能力によって、国家存亡の危機にまで陥ったことで、世論の声は一刻も早いミュータント管理システムを政府に求めた。その結果、ミュータント管理法案が異例の早さで成立、施行されたのだった。
施行から1ヶ月としないうちに、X-MENは解散を迫られた。エグゼビア教授はこれを承諾し、そのメンバーのほとんどが政府管理下に置かれることとなった。その時も、このエグゼビア邸は警官とFBIと殺気立った市民によって包囲されていた。以来、この広大な屋敷にはチャールズ・エグゼビアただ一人しか住んでいない。
「愛すべき教え子をすべて失い、お前はここで何をしようとしているのだ?」
再度、マグニートーがエグゼビアに問いを投げかけた。
「君こそ、なぜここにいるのかね、マグナス?」
「チャールズ!これがお前の理想とした世界の姿か?お前の言う平和とは何のためのものなのだ?我が同胞たちが苦渋をなめ、人間どもに平和を還元するためだったのか?」
「マグナス。その話は何度も繰り返してきたはずだ。そして、決して私と君の論が交わらぬことを、身をもって経験してきたはずだ。お互いの血と、名誉を汚してな。」
窓の外から邸宅を取り囲む人間たちの顔が見えた。
「もはや私とお前の理想は主義でも何でもない。お前がX-MENを率い、私がマグニートーとなったあの時から、すでに夢はついえていたのだ。」
「それは正しいな、マグナス。私はヒロイズムで、君はテロリズムで、それぞれ人を傷つけてきたにすぎないかもしれない。だが、それでも君と私は主義を捨てることができなかった。違うかね?」
「ではチャールズ、我々は何なのだ。何のための存在だったのだ。ホモ・スペリオールとは?ホモ・サピエンスとは?いや、答など出まい。ただひとつだけ確実に言えることがあるとすれば、この屋敷を囲む集団と我々の姿が、結論ではないということだ。」
「マグナス。君はいつも正しかったが、私には是も非も言う力がなかったのだ。」
「もうよい。友よ。」
それからわずかに15分後。エグゼビア邸は忽然と姿を消していた。地下にあったX-MENの施設もすべて消滅し、代わりにぽっかりと巨大な空洞が地下に広がっていた。エグゼビア邸を取り囲む者のなかで、邸宅の消滅の瞬間を記憶した者は、だれ一人としていなかった。
やがて、彼らがおそるおそる地下の空洞へと降りてゆくと、その底にあるものを発見することができた。
そこには車椅子と、その座席の上には赤い仮面が置かれてあった。
血の出る思いで書きました(笑)ホントはめちゃくちゃおバカ路線を考えていたんですが、煮詰めれば煮詰めるほど暗い方向に行ってしまい、結局コレっす。とりあえずマグ様の「ENOUGH(=もうよい)」を突っ込めただけで満足です、この場合。むつかしかったですホント。
(文責 田中。 2002/04/05)
いい天気だ。ぽかぽかと暖かい。1月初旬とは思えないほどの陽気だ。
おじ様の好きな日本なら「日本晴れ」とでもいうのだろうか。
金髪の小柄な、大人の女と呼ぶにはまだあどけなさの残るその女性は、住宅街を車椅子を押しながら目的地へ、そんな事を考えながら歩いていた。
車椅子には老人が座っていた。黒と白の混じった癖のある髪。昔はぎらぎらと獣のように輝いていたであろうくすんだ瞳。そしてすっかり皮と骨だけとなった細い手の甲に、乾ききった縦長の小さなかさぶたが3つずつ、治る気配もなく横に並んでくっついていた。
「いい天気ですね、おじさま。」
声を掛けても老人は無表情なままだ。しかしその女性には、かすかに微笑んだように見えた。
街中に差し掛かるとやけに騒々しくなった。パレードだ。1月1日は、毎年あちこちで記念行事が催される。ここマサチューセッツでは、特にその色合いが濃い。
街じゅうの人々が一目見ようと通りに押しかけている。町の真ん中を突き抜ける大通りには、大小のやぐら、派手なオープンカー、そして音楽隊の行進などが通りのはるか先まで続いている。パレードの行列の中には、派手なパフォーマンスをする人の姿も見える。
火をふく恰幅のいい男。様々な猛獣を後ろ足で立たせて見物客に手を振らせている少女。次から次へと別のやぐらに姿をあらわす道化風。中には派手すぎて恐ろしい事故につながるのではないか、と思えるものもあったが、見物客は、その芸を危険だと思う者はほとんどいない。
いや、芸でなく能力を。
そう、彼らはみなミュータントだからだ。
子供がもっと近くで見ようとパレードのための即席の柵を乗り越えようとする。とたんにそれを見つけた警官に襟首をつかまれる。「おとなしく向こう側で見るんだ。」そのアフリカ系の大柄な警官は、ひょいとその子を柵の外に連れ戻す。そして警備に戻ろうとパレードに向き直向き直った時、とおりの向こう側を郊外へむかって歩いている若い娘に押される車椅子の老人を見つけ、目を細めた。
(お気をつけて。)
時が時ならば顔に刺青を入れて、今よりももっと過酷な任務についていたであろうその男は、そう心で挨拶すると、改めてこの世界での自分に課せられた任務に専念し始めた。
「ジェームズさんだ!!」
校門の近くで遊んでいた少年が車椅子の老人を見て叫んだ。その声を聞きつけて、他の子供達もわらわらと集まってきた。
「ジェームズ先生、こんにちは!」
「ジェームズさーん!」
「ジェームズ先生!ジェームズ先生!」
たちまち子供達に囲まれて、身動きが取れなくなった。無理もない。ここは「天恵の子らの学園」。ミュータント解放の発端となったこの学園では、元X−MENは破格の扱いだ。とりわけ、生きた英雄ならば。
「ちょっ、ちょっと、みんなぁ。」
車椅子を押していた女性は、進めないもののたくさんの子供達に歓迎されまんざらでもなかった。が、このままではらちがあかない。行こうとしている先はまだもう少し先なのだ。
「君たち、嬉しいのはわかるが、クララさんが困っているでしょう。道を開けてあげなさい。」
その声を聞いた子供達は、渋々道を開け始めた。そしてモーゼの十戒のように出来上がった子供達の道の先に、その声の主が立っていた。
「ありがとうございます。ガスリー先生。」
ようやく進みだした車椅子を押しながらクララと呼ばれた女性は、その人物に声をかけた。
サム・ガスリー。
かつてX−MENに所属し、「キャノンボール」と呼ばれていた青年は、苦心の末にアメリカ大統領にまで上り詰め、ミュータント解放のために戦った。あいにく「ミュータント解放宣言」がなされたのは、彼が大統領を辞めたあとだったが。
現在はマサチューセッツでアメリカ中の「学園」を束ねる「エグゼビア財団」の名誉顧問に据えるかたわら、ここ最初の「天恵の子らの学園」の校長をしている。校長とは言うものの、彼はX−MENにいた時よりも少し皺が増え、たくましく成長したであろう貫禄は表れてはいるが、車椅子で無表情にたたずんでいる老人に比べればまだまだ青年だ。
あらためて不死のミュータント、エクスターナルである事を思い知らされる。
「こんにちは、ローガンさん。お元気そうで何よりです。」
サムは車椅子にかがみこみ、昔の通り名で声を掛けたが、老人は無表情のままだ。
「今日はようこそいらっしゃいました。ゆっくりしていって下さい。」
「…」
声は返ってこない。
ローガンと呼ばれた(現在はジェームズと名乗っている)この男は、数年前から自分の身体を支えられなくなって以来、郊外の病院で余生を送っていた。最近はめっきり口数も減っている。
「ごめんなさいね。おじ様はちゃんとわかっていらっしゃるんだけど。」
かつてサムの元で教育を受け、教鞭までとったクララには彼女のミュータント能力にかかわらず、この作り物のように微動だにもしない老人の考えが何故かわかるらしい。
「いや、かまわないよ。」
はみかみながらホッとしているクララに、サムは尋ねた。
「これからお父さんに会いに行くんだろう?」
クララは頷いた。
彼らの目線の先には、学園の道の先のはずれに柵で囲まれただだっぴろい広場があった。そしてサムは、少々戸惑いを感じながらも言った。
「お父さんも喜ぶよ。早くいってあげなさい。」
もう一度頷くと、クララは再び車椅子を押し始めた。
現在世のミュータント達は、「天恵の子らの学園」をなかば聖地としてみている。理由は2つ。
1つは1番最初の「天恵の子らの学園」発生の地であるということ。
いまやミュータントは、どこの町にもどこの国にも存在する。何人に1人がミュータントとかいうお話ではない。その世の中において、ミュータントと普通の子らを違う学校に入れることなどほぼ不可能だ。この「学園」でさえ、普通の子供を受け入れているくらいだ。もはやミュータントを守りX−MENを組織する「学園」の意味も薄れている。(現在「X−MEN」も国の組織だ)それでもここは聖地なのだ。すべてのミュータントが普通の学校に入学できるようになった、その最初の地なのだ。
だが、聖地化される理由はもうひとつある。ここには始まりと同じく、終りの地があるからだ。老人と少女の目的の地はそこにあった。
今年もいい年になりそうだ。
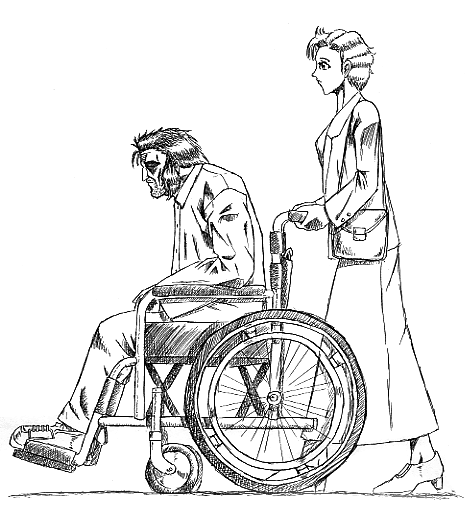
サムに見送られて(彼は後で改めて来ると言った。)先に進んだ2人は、高い柵に囲まれた広場の門をくぐった。門にはこう記してある。「天恵の子らの霊園」。ここにはミュータントの未来と理想の為に戦った英雄達が眠っている。「エグゼビア財団」が、敬意を込めて「学園」に併設したのだ。爽やかな日差しの中、クララと老人はさまざまな形や大きさをした墓石を横切ってゆく。墓石の中には、クララには馴染みのないミュータントの名前も記されている。
オータム・ロルフソン、ドミニク・ペトロフ、トーマス・キャシディ…。
かつてはヴィランと呼ばれた者達。彼らもミュータントの未来と理想の為に戦ったのだ。ここでは彼らにも平等に眠る権利があった。彼らのおかげで今の世の中があるのだ。
そんな馴染みのない名前だが、クララは自分の父の墓に毎年訪れていたので、憶えるでもなく記憶してしまっていた。
「フレッド・デュークス、レイヴン・ダークホルム…。」
覚えていた名前を無意識に呟きながら、クララはようやく父の眠る場所にたどり着いた。
「久しぶり、パパ。」
粗末な石の、亡くなった本人のイメージからはとてつもなく小さくささやかな墓標だ。墓石にはこう刻まれている。
『ビクター・クレイドン・クリード・シニアここに眠る ?〜2063』
生年月日がわからなかったので、生年は記されていない。生きている時は、昏睡状態からでも牙を剥いて襲ってきたものだったが、こうなっては見る影もない。彼の最後は、あっけないものだった。
クララは父のことをほとんど覚えていなかった。死ぬ直前に、父の古い知り合いと言う目の前の老人、ローガンに託されて今まで育ってきた。今では完全にローガンが彼女の父親だ。だから父のことはほとんど知らない。生みの親だという以外は。ローガンも詳しい事は教えてくれなかった。しかしただ一言。
「強かった」と。
そして毎年命日に墓に行きたがった。だから自分も父を尊敬した。
しかし、彼女は紛れもなくクリードの娘だった。齢50歳を越えても、少女の面影が消えない容姿。200ポンド近い体重を持つ老人を、車椅子に乗せて州の5分の1もの距離を長時間歩いてきても息1つ切れない強靭な体力。彼女は父に勝るとも劣らない強力な能力を持つミュータントだった。
ガスリー先生は私が行けば父が喜ぶと言った。しかしそのような経緯を持つクララはそう思わなかった。私が来る事よりも、この老人が会いに来る事のほうが喜ぶに違いない、と。そして、事実そうなのだろう。
声を発しない車椅子の老人に代わって、クララは声をかけた。
「今年も来たよ。元気だった?」
矛盾する質問を投げかけながら持ってきた花束を手向ける。
「おじ様が今年も来たいって。旧友の再会ってやつなの?私にはまだよくわからないな。」
クララは墓前でこんこんと話しつづける。
「でもね、他の人のことを聞いてかれても淡々と話すのに、パパの事はあまり話そうとしないの。なぜなのかな。よっぽどローガンさんはパパの事…」
話しかけて振り向いたクララは息を飲んだ。
「ローガン…さん?」
クララは、その場で立ちすくんだ。
ローガンが立っていたのだ。年齢を微塵にも感じさせない、力強い立ち方だった。
「クリード…」
老人は、数年ぶりに口を利いた。その声は、しわがれてはいたが、力強かった。
「見てみろよ、相棒。」
ローガンは、視線で街をうながした。
「全部、お前さんのおかげだ。あの日、お前がしてくれたことが、完璧じゃなくとも共存に向って努力するきっかけになったんだ。」
ローガンは、淡々と語った。クララは、老人の突然の挙動にたじろぎながらも、自分の体を支える体力もない老人をいたわり、再び車椅子に座らせようと近づいた。が、再びその場で立ちすくんだ。老人の手の甲から3本の爪が飛び出していた。彼の体力だ。きっとこの傷はこの先、完全に治る事はないだろう。老人は墓石に近づき、爪を振り上げた。
「今年は手ブラじゃ悪いと思ってな。」
そういうと老人は爪をふりおろし、墓石を切りつけた。
「プレゼントだ。」
そして何かを刻み付け、再び車椅子に腰をおろした。この老人にはもうたいした作業だったのだろう、肩を激しく上下させ、息を切らしていた。
「やっと思い出したんだ。一応もらっておいてくれ。もういらねえモンかも知れねえがな。」
そういうと、クララに向きなおり少し微笑むと、目で先をうながした。その先は、英雄X−MENの墓苑だ。クララはうなづくと、再び車椅子を押し始めた。そして自分の父親の墓を横目で見ながら、さよならの挨拶をした。
「じゃあ、また来年ね。パパ。」
墓石には、見知らぬ名前が刻み込まれていた。
生年月日とともに。
<おわり>
長いってば(笑)。
まあ、考え方としては、X−MENの最終回を描くとなると、それがなぜ始まったかとゆーところから逆算していって、単純にX−MENが終わる時は、いわゆる人間とミュータントとの共存が出来た時だろうなと単純に考えました。てことは、X−MENが終わる事はまずありえないのではないか(笑)と思うのですが、そんなんゆーと企画が破綻してしまうので、いちおー「ローガンのヒーリングファクターを持ってしても老化が抑えきれないくらいの未来ならどうかな?」とゆーだいぶ先の頃の話しとして設定してあります。んで、そーなるとライバルのセイバートゥースはどーなるのかとか考え、その(苦悩の)末に、かってにオリジナルキャラまで登場させてしまいました(誰だよ、クララって)。ホントは車椅子押す人がいれば、誰でもよかったんだけどね(笑)。
しかし、エグゼビアの存在なんか、どこ吹く風だな。いーや、軍曹も田中。ちゃんも教授だし。んで、いちおーここに描いてある分にはハッピーエンドっぽい終わり方にはなっているのですが、実はこのエンディングを書く前に指を滑らせて書いてしまった幻の(笑)バッドエンディングがありました。が、出来るだけのほほんとした最後にしたかったので、そっちをボツにして、こっちを発表させてもらいました。もしそっちが読みたい方は、メール下さい。個人的に送信します(しかも、そっちの方がよく出来てたりしてな)。しかし、こーゆーの書くと、手が抜けないのがモノ書きのヤなところですな(大した文でもないのに)。絵まで描いちゃって。(笑)。
でわでわ。
(文責 Lee 2002/06/13)
この日、アメリカは熱狂していた。いよいよ、次期合衆国大統領が決まるためだ。国民はこの瞬間を暖かい我が家や寂れた酒場、スタジアムに設置された巨大ビジョンなど様々な場所で待ちわびている。
候補は民主党候補のリチャード・スタインバーグ。
そして共和党候補で大統領に決まれば史上初の女性大統領となるエレナ・ヴァレン タイン。
両者ともある問題に対して主義主張が180°異なり、支持者がきれいにわかれてい る。
ある問題とは、これまで何度も議論がくり返されながらも、何故か結論には至ることなく収束していったミュータントの社会進出問題のことである。大規模なミュータント絡みの事件が発生する度に排斥運動が激化し、政府直属の特別機関が結成されることもあったが、如何なる理由からかいずれも自然消滅してしまい、一貫した国政とは言い難いものであった。
大統領候補はそれぞれ『ミュータントへの無条件での市民権確保』と『ミュータントを登録管理し強制収容』とで公約が異なり、市民権確保を謳うリチャード・スタインバーグは当初、圧倒的不利と予想されていたが選挙運動終盤になり徐々に支持者を増やす事となった。過熱する迫害運動に疑問を持つ者が増えた為である。
開票作業も終盤に差し掛かったようだ。
両者はこれまでの選挙運動を振り返り万感の想いで結果に挑んでいる。
長い道程であった。
自分達とは異なる者。異形の存在。
ミュータントの出現は、新たな紛争を巻き起こしたのだ。
人類にとって、異端者は眼を逸らし難い脅威であった。
ただし、彼等と話し合うチャンスを望んでいる者もいた。
ヒステリックに叫ぶだけでは問題の解決には繋がらないというのだ。
これまで人類は肌の色が違うと言うだけで、宗教観が違うというだけで多くの命を奪った。問題は異なれどその過ちから学ぼうとする人々も僅かながら確実に存在した。そして、日常的に出現するミュータントに慣れはじめ、冷静に客観視する人達が増えて来たのだ。
今回の国民の決断はミュータントの存亡に繋がる事を意味する。
そして、自らの未来をも決する事になる。
開票作業が終り、いよいよ大統領が決する時が来た。
選挙管理委員長がマイクを手にする。
「第**代アメリカ合衆国大統領は・・・・」
| ▼NEXT▼ | ▼NEXT▼ |
|
過去
雪深い山から麓へ延びるけもの道で少年は男と出逢った。男はうつぶせる形で雪上に身をさらし、上半身は一糸纏わず、凄まじい傷を負っていた。 「おじさん、大丈夫?」 少年の問い掛けに男は野獣が唸るごとく、到底、言葉とは呼べない返事をした。 声にならない声を聞き少年は慌てて雪に覆われた草むらに身を隠したが、おそるおそる男の方を眺めると信じられない光景を目の当たりにした。みるみるうちに男の傷が癒えているのだ。 呆然とその様子を眺めていると、突然、男が声を発した。 「そこから出てきな、ボウズ」 少年は戸惑い思案していたが、来ねぇならこっちから行くぞと脅され渋々出ていくことにした。 「誰かにやられたの?」 少年の問いに男は「あぁ」とだけ返事をし、しきりに鼻をひくつかせている。その仕種はまるで餌となる獲物を探す肉食獣そのものだ。 「どうやら諦めたみてぇだな」 そう呟くと少年の方に振り返り、脅してすまなかったと語り掛けた。 少年はこの非現実的な出会いにいたく感激したらしく眼を輝かせている。 「おじさんは誰?どうしてケガがすぐ治るの?ヒーローなの?」 「ボウズ、落ち着きな。いっぺんに聴かれても答えられねぇぞ」 そう答えながら、鋭い眼差しで辺りを見回し何かを窺っている。追手らしき者がいない事を視覚でも確認した男は少年に向き直り、答えた。 「まず、俺はヒーローじゃねぇ。ミュータントだ」 男はなぜ傷が瞬時に癒えるのか簡単に説明し、続けた。 「それから俺の名はローガンだ・・・」 |
過去
どれだけ気を失っていたのだろう。 一瞬の出来事だった。 強烈な閃光で眼が見えなくなり、何が起こったのか理解出来ないまま凄まじい爆風と激しい爆音に呑み込まれ私は地面に投げ出された。 徐々に戻ってくる視界にアスファルトと白線が映り、自分が車道にいると気付く。 "こんな所に居てはいけない。轢かれる。" 脳はそう判断したが俯せに投げ出された私の身体は動かない。いや、動かせないのだ。 もう一度、身体に力を入れてみる。緩慢にだが腕は伸びた。全身に力を込める。 大丈夫。なんとか動くようだ。まず、上体を起こし、重い頭を左右に動かしてみる。どうやら頭も無事らしい。 鮮明になってきたアスファルトからそのまま視線を周囲に向けると想像を絶する世 界が拡がっていた。 気を失う前、確かに私の目の前にあったビルがない。いや、正確に言うなら瓦礫の山と化している。その周りも同様に、瓦解し突如生まれた空間に煙のような埃がただ舞っている。周りも眼を覆いたくなる光景だった。 あこちこで火の手が上がり、コンクリートやガラスの破片が私の服の上にも降り注 いだようだ。 何があったのだろう。ふいに思い出す。パパとママは? 再び周囲に目を向ける。いない。反対側を見回す。やはりいない。 振り返り、ほんの少し離れた場所に眼がいった。 あっと息を飲んだ、横転し大破した車の下に見覚えのある手を見つけたのだ。その手は別のもう1人の手と堅く握りしめ合っている。お揃いのペアリングが光る。心臓が早鐘を打つ。嘘だ。信じない。急いでそばに駆け寄ってみる。見間違えようがない。私の両親の手だ。2人の手を握りしめる。涙が止まらなく、気が狂いそうになる。 周囲の騒音が激しくなってきた。サイレンの音と人々の怒声、あちこちで火が爆ぜる音が聴こえる。聴覚も戻ってきたようだ。 ふいに人々の叫び声が強くなった気がした。 よく聴き取れないが方々で「ミューティーが・・・」と叫んでいるようだ。背後で爆発が起きた。最初のそれと比べて小規模な爆発だ。音の方へと振り返る。涙で視界が霞みよくわからないが黒い影が私めがけて飛んできた。 避ける暇もなく直撃する。 激痛が全身を襲う。何かが私の上に覆い被さっている。頭が痛い。さっきのショックで頭を強打したらしい。身体に乗っている物を退かそうと試みる。重い。耐え難い重さが全身にのしかかる。 眼を開き確認する。どうやら誰かが私の上にいるようだ。男性と思われるその身体を押し退けようと私は懸命に足掻いた。ふと、その男性の飛んできた方向に焦点が合う。何かが動いた。眼を凝らしてみる。 人だ。人がこちらに向かってやって来る。 炎を背にし、こちらからは表情が伺い知れない。 再び激痛が頭を襲う。眼が霞みだした。 眼の前が白んでいくなか、私は見た。 私に向かって、構えるようにして腕を突き出し、手の甲から長い爪が突き出るのを・・・ |
| ▼NEXT▼ | ▼NEXT▼ |
|
現在
開票作業が終るまでのあいだ私は過去に出逢ったある人物の事を想い出していた。ローガンという不思議な力を持った男の事だ。 何者かに襲われ全身に傷を負っていたが、私の眼の前で傷が癒えていった。彼曰く、ヒーリングファクター(超回復因子)というものの作用であるらしい。私が出逢った初めてのミュータントである。 それまで私は周囲の人間からミュータントについてあまり良い話は聞かず、幼いながらも偏見を抱いていたのだが、彼はいままでの話とは違い、人間である私に穏やかに接してくれたのだった。 むしろ、私の両親などよりも優しい眼差しを私に向けてくれたと感じた。 彼は自分がミュータントであるが故に、様々な組織から狙われ、人々から疎まれて いたのだと言う。だが、そんな過酷な境遇に屈する様子など全く見せず、彼は冗談まじりで私の相手 をしてくれた。今まで出逢った誰よりも人間臭く、僅かな時間の出逢いではあったが確実に私を変 えてくれたのだ。 その後、TVなどでミュータント絡みの事件が報道される事が増え、周りの人々はミュータントに対してあからさまな嫌悪感・敵意を示し、「政府の介入による秩序を」と唱えだしたのだが、私にはブラウン管に映るミュータント達が悪意を持って罪を犯しているとはどうしても思えなかった。 そう、私の眼には虐げられ行き場を失った者達の最後の抵抗に映ったのだ。 確かに、中には悪意ある犯罪者もいただろう。だが、そういった者達はたとえミュータントでなかったとしても同じ道を歩んでいたのではないだろうか。 私はいつまでもその気持ちが拭えず、「ミュータントとの対話」を信念に政界へ入ったのだが周囲の環境は決して私に居心地の良いものではなかった。 我が党のタカ派はあくまでも反ミュータント主義をスローガンに活動し、ハト派である主流派も概ねそれにならっていた。私のような擁護派━━私自身、擁護しているつもりはないが━━は極めて少なく、また世論に逆らっているとして決して陽の当たる場所に任ぜられる事はなかった。 ただ、激しすぎる潮流には必ず逆流が生まれる。それが私に味方した。 我が党のタカ派をも凌ぐ過激な運動で圧倒的な支持率を集めていた共和党がその運動を強めた為、あちこちで疑問の声が噴出したのだ。 党の主脳陣はこの流れに便乗し形勢の逆転をと、急遽擁護派の中でも具体案を提示し続けていた私に白羽の矢を立てたのだった。 私は傀儡なのかも知れない。だが、ただのあやつり人形では終らない。 ミュータント問題に関しては私の全人生を賭けて信念を貫き通すつもりだ。 周囲に促され、壇上へ向かう。割れんばかりの拍手が私を待っていた。 |
現在
選挙管理委員長の口から彼女の名が告げられ、大統領選は幕を閉じた。 合衆国史上初の女性大統領の誕生である。そして、ミュータントにとってはそれ以上の意味を持った瞬間でもある。 ミュータントの強制収容。 この公約は選挙以前から一貫して通しており、またこの公約のお陰で当選したと言っても過言ではない。相次ぐミュータント問題。新人類と呼ばれる者達の蛮行により多くの市民の血が流 された。 彼等のテロリズムは激化し、もはや1日を平和に暮らす事も難しくなっている。人々の不安や憤りから自然と拡大していった反ミュータント運動。 そして、彼女もまた犠牲者の1人であった。 ミュータントがきっかけだと思われるビル爆破事件に巻き込まれ両親を一度に失い、自らもまた生命の危機に瀕した事があるのだ。 手の甲に生えた爪。それが彼女の生命を狙った男の特徴であった。 炎を背にし、よく見えなかったがあの悪魔のような爪だけは忘れる事が出来ない。もう何年も経つが今でも悪夢となって蘇る。 ━━私の生命を奪おうとしたあのミュータントが両親をも殺したのだ。こんな悲劇はもうくり返したくない。 その想いだけで今日までやって来たのだ。 そして、ようやくその想いが結実する日を迎えるコトができた。これで平和に暮らせる世界を取り戻せる。彼女は希望に満ちた眼差しで観衆を見渡した。 マスコミに向けてのコメントを発する。 「みなさん、ありがとう。みなさんの支持のお陰で大統領となる事が出来ました」 「この結果は、国民の総意として真摯に受け止め、最優先事項として全力を持って問題解決にあたりたいと思います」 割れんばかりの拍手が会場を埋め尽くす。 「早速ですが、まず大統領命令として公式・非公式を問わず全てのミュータント・コミュニティの解体を命じます」 「次に来年度までに全てのミュータントを管理システムに登録し政府直属の施設に収容します」 「彼等に我々の日常を壊す権利はありません。今度は我々が裁きを与えましょう」 ついに永年の因縁に決着をつける時がきたのだ。 観衆は喜びに打ち震え、熱狂は会場を揺るがす程にまで高まった。 「みなさん、我々の平和はすぐそこです。人類の新しい第一歩を共に歩んでいきましよう!」 |
| THE END | THE END |
大変お待たせしました。3ヶ月以上も更新を滞らせていたのは僕です。
ただ、粘った分、僕的に納得のいくモノが出来たと思ってます。
みんながX-MENを中心に書いてますが、アマノジャクなんで人類中心に書いてみました。X-MENじゃねーじゃんと言うツッコみは却下です。
お話的にはifの中のifと言う感じで逃げた感が強いですが、僕の中でどうしても表現したかったのはX-MENの活動とは直接的に関係のない結末を作るコトによって、彼等の活動が報われなかったという皮肉と、状況や環境の違いにより同じ人物と出逢っても受ける印象が違い、それが大きな結果に繋がるというパラドックスでした。別にローガンさんじゃなくても良かったんですが、自分の好きなキャラの方がイメージしやすかっただけなんで、お気に召さない方は自分の好きなキャラに置き換えて読んでみるのも面白いかも知れません。
ストーリーは、現実的におかしな部分があるのは承知してますが、まぁ、アメリカの文化、ましてや政界のコトなんて知らないし遊びだからなと開き直って好き勝手させてもらいました。設定など深く掘り下げなかったのは、みなさんの想像力で補完してもらおうと思ったからです。自由度がある方が良いでしょ?
産まれて初めて小説なんて書きましたがしんどいです。死にそうでした。しかも、後先考えずに書くからみんなと比べてえらい長くなってるし・・・。バカ丸出しです。さて、大トリを努める組長の最終回はどんなオチでしょうか?期待でいっぱいです。
こんな稚拙な駄文に最後まで付き合って下さってホントに有り難うございました。
(文責 DIE 2002/10/02)
(文責 吉田司郎 2002/10/31)
すいません.うちの吉田が...(笑)
企画者のえむはし軍曹です.今回はお題の難しさもあってかなり苦戦しましたね.X-MENという長年続いていたコミックにどのような幕を下ろすのか,色んな考えがあるでしょうが,やはりX-MENというシリーズの性質上,イデオロギー対立にどのような幕引きを与えるのかがテーマになっていたような気がします.特に田中。,DIE両氏の結末は物語の中心と周辺という視点の違いはあれど,イデオロギー対立の幕引きをうまく表現できていたと思います.見事です!正直どのように幕を引いていいのか分からず,自分はその結末を書かないという逃げをしてしまいました.それに対してDIEさんはIF形式というかなり反則技(笑)をつかって回避するなど面白かったです.また,マグニートーと教授という非常に難しい核心部分を書ききった田中。の力作には脱帽です.かっこいいね.
一方,Leeさんはそれを越えたところでのウルヴァリンとセイバートゥースのライバル心を中心にえがいてくれました.イラストつきなのでびっくりしましたが,やはりローガンは死ぬまで爪だしてそうですね(笑).X-MENの魅力はイデオロギー対立のみならず,個と個の人間関係が生み出すダイナミクスにもその一端があったりします.こういうパターンの最終回はどの組み合わせでも面白いドラマがうまれそうですね.敢えて教授に絞らずX-MENメンバーの人間関係でおしたという点でユニークなのではないでしょうか?
で,最後の問題作,吉田司郎(笑).原稿送られてきたときは悪い冗談だと思ったんだがなぁ(笑).でも,実際メタな視点で考えると,Marvelがそう簡単にX-MENに幕を引くとは考えにくいので,本当に終わるとしたら実は吉田案が一番妥当なのかと(笑).
いろんなパターンの最終回がありましたが,実際どうなるんでしょうね?生きている間に見たい気もするし,見てみたくない気もします.差別や偏見がなくならない限り終わらない物語であることは誰でも承知しているところです.もし終わるとしたらイデオロギー問題の解消ではなく,キャラクタービジネスの賞味期限切れということになるでしょうな.その日までX-MENには第一線でがんばってもらいたいものです.
倒産するなよ,Marvel !! ってことでこのシリーズの幕を引かせて頂きます.長い間ありがとうございました.
(文責 えむはし軍曹 2002/10/31)
ココチヨク……アタタカク……コモレビノヨウナ……フユウカン
「今日は休日だろう」
エリックの口調は忠告に近かった。
「休日は休むためにあるのではないのかね?」
言い終わらないうちに、彼には答えが分かっていた。眼前の紳士チャールズ・エグゼビアは、休息に最も無縁の存在なのだ。今、こうしてソファに腰かけているわずかな時間ですら惜しむような男なのである。
「分かっているよ、エリック」
プロフェッサーXことチャールズ・エグゼビアが、車椅子とも杖とも決別してから、もう何年にもなる。
「だが、今日はみんなが私に会いに来るのだ。サイロックに会うのは久しぶりだしな。疲れたといって寝ているわけにもいくまい」
そう言っているエグゼビアの表情は柔和で、日頃の激務を微塵も感じさせない。ここ一週間の睡眠時間は、10時間を切っているはずなのに。
―まったくもってたいした活力だ!―
マグナスは苦笑する。だが、この活力があったからこそ。チャールズ・エグゼビアとX-MENは、夢を勝ち取ることができたのだ。
友人の言わんとしていることが分かったのだろう。
エグゼビアは窓の向こうに視線を移す。
そこには、外の世界が広がっている。
外の世界。そこには、穏やかな日射しが降り注いでいる。空気はどこまでも澄んでいた。ミュータントと人類の間に、もはや壁などない。今や、「ミュータント差別」という単語自体、歴史の1ページになりつつある。
エグゼビアにとって、親友の存在はありがたかった。かつて一度も敵対したことのない親友エリック。彼なしには、夢は潰えていたことだろう。
「朝食を済ませたら、すぐに出ようと思う」
そう言ってソファから立ち上がる。その時、不意に、目眩と共に違和感がエグゼビアを襲った。
「どうした?」
「いや……」
違和感の正体。それが何なのか、分かるようで分からない。いや、分からないようで分かるのかもしれない。それは思考の焦点を合わせれば容易に見えるようで、それなのに見てはいけないもののような気がした。
「なんでもない」
「そうか」
エリックはたいして気にしていないようだった。
「今日は、サイロックの他に誰が来るんだ?」
「今日……来るのは……」
違和感が拭えない。頭が赤と白に明滅する。沼の上に立っているかのように、足場が不安定になる。
「サイロックの後…………シャドウキャットとコロッサスの夫婦…キティは妊娠27か月目でそろそろ安定期……モイラも来るし……リランドラ……シャイアの皇帝…私の妻?……ウルヴァリンとセイバートゥースは昔からの親友……喧嘩をしたこともなく……」
「どうした?チャールズ?」
エリックが支えようとする。その手を、彼は咄嗟に振り払った。親友の驚いた目が自分を見つめる。
「どうしたというのだ?」
「おかしい……これはおかしい……」
頭が熱い。風景が歪む。全身を支えていられない。エグゼビアは、その場に膝をついた。
「ありえない……私と君は、ずっと敵同士だったはずだ!サイロックもコロッサスも死んだ!モイラもだ!リランドラとは結ばれなかった!ウルヴァリンとセイバートゥースは獣のように憎しみあっている!なんだ?この世界はなんだ?これは……これは……」
「……ールズ!チャールズ!」
聞き慣れたその声でエグゼビアは目を覚ました。柔らかなオルゴールの旋律のような声。目を開けると、そこには紅い髪の、最も古くからの教え子の一人、フェニックスことジーン・グレイ・サマーズの顔があった。気のせいか、少しやつれて見える。
「どうなさいました?」
「ジーンか……夢を見ていたようだ」
体を横にしたままで、エグゼビアは弱々しく笑った。
「どんな夢です?」
「私の理想通りの世界だった。エリック……マグニートーとは袂を分かつことなく、死んだ教え子達も生きており、心痛む争いもない……そんな世界の夢を見ていた……」
「疲れているんですわ、教授」
フェニックスがエグゼビアの額に手を乗せる。それはひんやりとして、彼の心を落ち着かせた。現実への帰還を認識する。
「まだ熱が下がっていないみたいですね」
「熱……そうか、私は熱があるのか……」
「そうです。もう少し、お休みになっていた方がよろしいかと」
「そうだな……その通りだ……眠ることにしよう……」
そして。
チャールズ・エグゼビアは、また、深い眠りへと落ちて行った。
「どうだった?」
夫の声に、振り返らずにフェニックスは首を振る。
「また目を覚ましてしまったわ……やっぱり、教授ほどのテレパスに幻影を見せ続けるのはたいへんよ……どんな理想郷を見せても矛盾に気づいて現実に帰ってきてしまう……」
「だが、そうしてやるのが我々のせめてもの恩返しだ」
サイクロップスことスコット・サマーズの口調には疲労感が滲んでいた。
「我々の行動を教授が知ったら、きっと激怒するだろう。だが、教授にこの世界は見せられない。彼が、もし、この世界を知ってしまったら……」
スコットは窓の向こうに視線を移す。
そこには、外の世界が広がっている。
外の世界。そこには……。
(文責 PK 2002/11/11)
ヤミナベユニバースのPKさんに寄稿していただきました!夢オチってやつですが,夢を見させられている人と,夢を見させている人の二重構造ってのが面白いですね.で,やっぱり平和的共存は生まれないというバッドエンド.話の性質上,X-MENの落とし所ってのは相当むずかしいなと改めて感じる次第..
PKさん,寄稿ありがとうございました!
(文責 えむはし軍曹 2002/11/11)